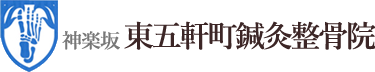2023年、厚生労働省の人口動態統計によると日本人の主な死因の第1位は悪性新生物で24.3%、2位は心疾患で14.7%、3位は老衰で12.1%、4位は脳血管疾患で6.6%です。心疾患と脳血管疾患を合わせることにより見えてくる事は、日本人のおよそ5人に1人が循環器由来の病気によりなくなっていると言うことです。
これにはかなりの確率で動脈硬化が関係しています。動脈硬化の進行を抑えて予防するには生活習慣の改善が必須です。
動脈硬化とは?
動脈硬化とは、動脈の壁が厚く、硬くなり、弾力性が失われた状態のことをいいます。主な原因の一つは高血圧です。血圧が高いと血管に負荷がかかり、それが慢性的になることで血管が硬く痛みやすくなるのです。血液中のLD Lコレステロールが多くても動脈硬化を引き起こします。LDLコレステロールが多いと、血管の壁に入り込んでプラークを形成する事で血管内が狭くなります。すると血栓などが詰まりやすくなったり、プラークがたくさん出来て血管内が狭くなると、同時に血管壁が厚く硬くなるため、動脈硬化に繋がるのです。
動脈硬化の原因は?
動脈硬化の要因は、加齢、喫煙、高血圧、脂質異常症、糖尿病、家族歴、慢性腎臓病、肥満、運動不足、過剰な飲酒、ストレスなどです。
血液検査の大切さ
特に食事はとても大切です。脂質の多い食事をしていると中性脂肪やLD Lコレステロールが増えます。これらは健康診断の血液検査を受けることで、今自分がどのような状態にあるのかを把握することができます。日ごろの食生活に自信がない場合はぜひ検診を受けて血液検査の結果を見てみることです。
食生活の改善
もしも食生活を改善するのならば、家族や夫婦で管理栄養士の指導を受けるのが大切です。「食べる人」だけでなく、「作る人」の意識もアップデートする事が肝要なのです。
食事見直しの第一歩は、お肉や揚げ物が主である飽和脂肪酸を多く含む食事から、不飽和脂肪酸を多く含む魚や植物性食品が中心の食生活に改めることです。
他にも、ヨーグルトは低脂肪のもの、牛乳は無調整豆乳に置き換えるとか、野菜を増やし食物繊維積極的に取り入れることも1つです。早ければ1、2ヶ月で効果が現れます。
適切な食事メニューに変更すれば、食事の量そのものを無理に減らす必要はないのです。
かといって脂質は全く取らなくてもいいと言うわけではありません。バランスの取れた脂肪とコレステロールが少ない食品を選ぶことが必要なのです。
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸
LDLコレステロールを上げやすい飽和脂肪酸から、LDLコレステロールを上げにくい不飽和脂肪酸にする事を心がけてください。
L DLコレステロール上げにくい食材としては、EPA 、DHAを多く含む鯖、イワシなどの青魚や、オリーブオイル、リノール油が含まれるナッツや大豆などがオススメです。しかし、オイルは油ですので摂取量に注意して下さい。
動物性タンパク質、すなわちお肉をたべるならばヒレなどの赤身肉や鶏肉がいいです。しかし、鶏肉の皮にはコレステロールや飽和脂肪酸が多く含まれています。そして鳥の卵にもコレステロールが多く含まれています。そのため、LDLコレステロールが高い人の卵の摂取は2日に1個程度にしてください。
糖質
糖質を過剰摂取すると血糖値が急上昇し、それをさげるためにインスリンが過剰分泌されます。血糖値の急激な上げ下げは血管に負荷がかかるため動脈硬化のリスクや肥満につながる恐れがあります。
そして、白米は炭水化物が多く含まれます。炭水化物は代謝されると糖質になるので、糖尿病や動脈硬化症を患っている方、コレステロールが高い方は白米の摂取量に注意して下さい。
一方で玄米、大麦などは糖質が少なく、LDLコレステロールの上昇を抑える食物繊維を多く含んでいます。
他にも、水溶性食物繊維は脂質や血糖の上昇を抑える働きがあります。
水溶性食物繊維を多く含む食材
玄米、大麦、オートミール、わかめ、昆布、納豆、ごぼう、アボカドなど。
食塩の摂りすぎにも注意
食塩をたくさん取ると血中の塩分濃度を薄めようとして血液中に大量に水分を取り込みます。量が増えた血液を全身に送るためには強い圧が必要となるため、血圧が上昇するのです。それが慢性化すると血管に負荷がかかり動脈硬化を招きます。
食塩はあまり取らないようにするためには、食塩の過剰摂取を控えるとともに、カリウムを多く含む食品を取ることが肝要です。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出する性質があります。
カリウムを多く含む食材
りんご、バナナ、ほうれん草、里芋、納豆
1日の摂取カロリーの目安
30から49歳
男性 2650キロカロリー 女性 2000キロカロリー
50から69歳
男性 2400キロカロリー 女性 1800キロカロリー
70歳以上
男性 2200キロカロリー 女性 1700キロカロリー
※あくまでこれは目安です。体重や活動量によってこれらは異なるため摂取量は専門家に相談して決めてください。