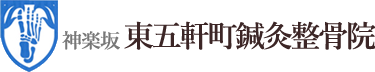「笑い」とはなにか?人はなぜ笑うのか?今回は笑いについて自分なりに考えていこうと思う。
まず、「笑う」事ができる生物は自然界において少ない。特に、何らかのユーモアに対して笑いを持ってリアクションするのは、ほぼ人間のみと言ってもいいだろう。一部、イルカやチンパンジーなどが仲間内で「笑い遊び」なる行為をするらしいが、それが人間と同質のものなのかは推測の域をまだ出ていない。
動物の「笑い」については以前、「猿の笑顔」について興味深い話をテレビで見聞きした事がある。
専門家が言うに、猿の笑顔は「威嚇」か「服従」かの意思表示だという。自然界において同族の敵と相対した際、基本的には戦うか服従するかの2択。戦いを選んだならば、戦闘の意思を示さねばならない。その時に使うのが「笑顔」だ。しかし、笑顔といっても我々が思う笑顔とは少しニュアンスが違う。口を開けて歯を剥き出して、目元もクシャッとなるため一見、笑顔の条件を満たしているようにも見えるが、これは相手を威嚇している証拠なのだ。
一方、勝てなさそうな相手と対峙した時や、分が悪いと踏んで争いを避ける時は「服従の笑顔」を見せる。「私はあなたと事を構える気はありません」という意思表示だ。争いを避けるための力の無い笑顔、これは要するに我々ホモサピエンスでいうところの「愛想笑い」に他ならない。
これだけ見ると「なんだ、人間は常に愛想笑いをしているから、猿と同じだと言いたいのか?」と思う方もいるかもしれない。………まあ大方、我々も猿と同じなのだと思う(笑)しかし「服従の笑顔」というと聞こえは悪いが、「愛想笑い」は無用な争いを避けるための世界共通マナーであり、優れたコミニュケーション術といえる。別に愛想笑いを相手より先にしたからと負けた気分にはならないし、ほとんど無意識で行っている。マクドナルドでは愛想笑いがプライスレスで売られているくらい、コストを必要とせずに相手との友好的な空間を瞬時に創り上げることができる。
しかし時として、愛想笑いの弊害もある。それは、相手が愛想笑いをしていても100%友好的と断定できないケースもあるという事。我々は猿とは違い、大脳、特に理性脳である前頭前野が大きく発達している。そもそも「ホモサピエンス」とは賢い人族という意味だ。そのため「愛想笑い」をして表では友好的な意思を示していたとしても、その裏で非友好的な悪意を秘めていて、それを上手に隠している可能性があるという事だ。そして、我々ホモサピエンスは賢いがゆえに、それが実行可能な生き物なのだ。
同じようなスーツで身を包んだ世界の首脳達が一堂に会して、ニコニコしながら握手をしている場面。あれこそまさに全員、肚では何を考えてるか解ったものではなく、ニコニコしてても警戒せねばならない状態だろう。トップが集まる場においては、不用意な言動で言質を取られ、あっという間に自国が不利な状況に陥る危険性がある。遠慮していては足元を掬われるだろうし、利益も得られず自然と「格付け」が形成されてしまう。だからといって、なんの勝算もなしに強気な姿勢を誇示し続けるのも得策ではない。そのような場面は、互いに武器こそ持っていないが「戦闘中」といっても過言ではない。ここが我々と猿とで大きく異なる点だ。
なにも、政治関係者の取引や会談だけに限らず、このような「戦い」は、規模の大小こそあれ社会生活を営む人間ならば日々経験している。魅力的な「服従の笑顔」を携えた営業マンや詐欺師などがいい例だ。「愛想笑い」を常にオートで発動させつつ、理性脳をフル回転させて自分を守りながら戦う、これこそが現代を生きるヒト科の人族ホモサピエンスの「戦い」の形なのだ。
だが、人間は時としてなんの忖度もなく、掛け値なしに面白くて笑ってしまう事がある。これこそが真の「笑い」であり、身体にも良い影響を及ぼす事が解っている。笑いと健康の相関性についての研究や臨床結果を以下に示す。
①今から60年前にアメリカのノーマン・カズンズというジャーナリストが自己免疫性の疾患で苦しんでいた際、「笑う」という行為に重きをおいた。10分間寝る前に腹を抱えて笑うと、病気による身体症状があるにも関わらず2時間ぐっすり眠れた。そのメカニズムはわかってないが「笑い」は深い呼吸、自律神経の調整などに良いという結論に至った。
②1995年に日本医科大学にリウマチの患者を集めて、林家喜久蔵さんが落語を行った。その前後で被験者に血液検査をした結果、リウマチの炎症を引き起こす物質が全員、半分以下になっていた。
③2003年には筑波大学で糖尿病の人に漫才を聞かせる実験を行なった際にはほとんどの人の血糖値が下がった。
④2017年大阪国際がんセンターにて、「笑い」がNK細胞の活性化を促進する事を確認した。
⑤福島県立医科大学の大平教授によると、65歳以上の1000人を対象に調査した結果、ほとんど笑ってない人は毎日笑ってる人より2倍以上認知機能が低下してる割合が多い事がわかった。
⑥大阪大学の2022年の研究によると、毎日笑う人はそうでない人と比べて認知症のリスクが26%軽減する事も分っている。
1995年に生まれ、世界110カ国に広がっている笑いの体操と呼吸法を融合した「笑いヨガ」なるものもある。
笑いヨガは、「手拍子」「掛け声」「深呼吸」「子供に帰る」「笑いの体操」の5つの要素からなる。
「手拍子」はリズミカルに手を叩きながら「ホッ、ハッ」という。これをすると大笑いした時と同じような呼吸器の動きになる。
「掛け声」と「子供帰り」は、はしゃぐ子供のように「いえーーい」と言いながらバンザイする。この時、大きな声を出すと同時に思い切って童心に戻る事が大切。
「深呼吸」と「笑い体操」は、アーーーといいながらお辞儀してローーーといいながらのけぞり、大きく息を吸って「ははははははは」と笑いながらもう一度お辞儀する。このアロハ笑い、もとい「笑い体操」で呼吸筋が鍛えられる。これがストレスを発散させる笑いとなるらしい。
あと、嫌な事があった時のストレス発散法としては、あえてもう一度嫌な事を笑いながら再現するのも一つ。例えば、間違って足がゴミ箱に当たって中身が派手に散らかり、痛みとケアレスミス、時間の無駄に対してイラつきを覚えた際は、片付けた後にもう一度散らかすふりをりして笑うのだ。笑いながらしくじった事をもう一度、大袈裟に再現しているとだんだんどうでも良くなってくるものだ。
「笑い」は仮に作り笑いでも脳は錯覚して、本当に楽しい状態なのだと判断するという。そして、大笑いした時と同じようなバイタルと身体の状態になると、よりリアルに脳は大笑いしたと錯覚する。
日常生活で、たとえ面白い事が何一つなかったとしても、1日1回でいいから肺呼吸器、腹筋、顔の筋肉、血圧など「大笑い」した時のそれと同じような状態を再現してみてほしい。恐らく脳、身体はその刺激を定期的に必要としている。だからこそ上記のような、身体にとって良い反応が起こるのではないか。猿の笑いは「威嚇」と「服従」の二つだが、我々人類の笑いは「悪意なき平和のための愛想笑い」と「健全な大笑い」の二つになるといいなと思う。