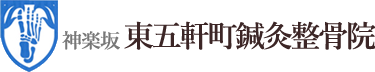ビタミンDが欠乏するとカルシウムを吸収できずに骨が柔らかくなる骨軟化症を招きます。
小児の場合はこれをくる病といいます。
最近、このくる病が増えています。日本小児科学会の調べによると生後5ヶ月までの乳児の52%がビタミンD欠乏症であり、その原因としては食事を含めた生活環境の変化にあるとしています。
ビタミンDは骨を丈夫にする役割があり、小腸においてカルシウムやリンの吸収を促進するように働きます。
ビタミンDが欠乏すると、一歳未満の子供の場合は血液中のカルシウムが不足する事で全身の筋痙攣、硬直を招きます。一歳以上の子供の場合は、O脚、X脚、歩行障害などが現れます。乳児期のビタミンD欠乏が、幼児期のくる病につながるのです。
0歳から15歳までのビタミンD欠乏症の有病率は、2009年から2014年までの間に約3倍以上に増加しています。※Itoh M al.Global Pediatr Helth 2017より
ビタミンDが少なくてもカルシウムが豊富にあれば骨の脆弱性をカバーでき、易骨折を防ぐ事ができるでしょう。
しかし、母親がビタミンD欠乏症だと生まれてくる赤ちゃんもビタミンD欠乏の状態で生まれてくる傾向にあります。
妊娠初期から出産一年後までの母親68人を対象とした調査によると、妊娠初期から産後の6ヶ月までずっとビタミンD欠乏の状態が続いている事がわかりました。
※Yoshikata H et al.J Bone Miner Metab 2020より
これは妊娠してなければビタミンDが欠乏しないのではないかと思いがちなのですが、妊娠していない女性30人を調べた場合でもその多くがビタミンD欠乏状態でした。
実は日本人女性はビタミンD欠乏症の方が多く、さらには中学、高校の女生徒のおよそ47%がビタミンD欠乏症であることがわかっているのです。
その理由としては、①日光を浴びないことにあります。
ビタミンDの80%は日光(紫外線)を浴びる事で皮膚上で作られます。残りの20%は食事で合成されるのです。
そのため、日焼けを嫌がって日焼け止めや衣服で皮膚を覆う事でビタミンD合成が阻害されているのです。
日本人は食事でビタミンDを摂る時、その80%は魚から摂っています。
最近は集合住宅が増えての排煙の関係、外国の乱獲、気候変動などで魚を食べる機会が少なくなりました。
そのため、母乳栄養で子供を育てている方の子供さんの77%がビタミンDが少ないのです。粉ミルクの中にはビタミンDも入って入るので、粉ミルクで育てているの子供さんは21%が欠乏症でした。
しかし、だかりといって必ず粉ミルクにした方がいいわけではなく、母乳には貴重な免疫細胞や様々な利点があります。離乳食と合わせてなど、臨機応変な対処が肝要です。
ビタミンDを合成するためには1日に2から3回ほど外出をすると良いです。屋内にいて、ガラス越しに日光を浴びても効果はありません。暑い夏の外出はくれぐれも無理しないでください。
ビタミンDは多すぎると高カルシウム血症になることもあるので大量に摂り過ぎるのもよくありません。
気になる方は日光を適度に浴びることと食事を気にしてみてください。