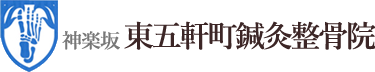65歳以上の方で100人に1人の割合で罹患しています。
パーキンソン病は脳と神経の病気です。
歳のせいだと思い込むと受診と発見が遅れます。
症状
動作緩慢
手足の震え
突進歩行
小刻み歩行
仮面様顔貌
筋強剛
姿勢保持障害
など。
発生機序
大脳の下にある中脳黒質では、ドパミン神経細胞がドパミンを作ります。
ドパミンは大脳からの指令を調節して、体をスムーズに動かすために必要な物質です。
また、ドパミンが作られると楽しい気持ちになり、やる気にも関与します。
パーキンソン病は、ドパミン神経細胞が減少し、ドパミンが減る事で発症します。
なぜドパミン神経細胞が減るのか?
はっきりした事は解っていません。
体質的な要素、加齢、生活環境など、いくつかの要因が加わって起こると考えられています。
パーキンソン病の非運動症状
(精神症状)
うつ
不安
パニック発作
(睡眠障害)
不眠
日中の眠気
レム睡眠行動異常症
(自律神経障害)
便秘
排尿障害
起立性低血圧
(感覚障害)
痛み
嗅覚障害
早期に出る症状
うつ
レム睡眠行動異常症
便秘
嗅覚障害
気になる症状があれば、脳神経内科を受診してください。
画像検査など
(ドパミントランスポーターシンチグラフィ)
脳の中のドパミン神経細胞の障害を評価する検査です。
(MIBG心筋シンチグラフィ)
心臓の交感神経を評価する検査です。
(MRI)
脳の病気がないか確認します。
(嗅覚検査)
嗅覚障害を調べます。
薬物療法
(L-ドパ製剤)
腸から吸収されて脳内へドパミン神経細胞に取り込まれてドパミンになります。
デバイス補助療法
(DBS 脳深部刺激療法)
胸に埋め込んだ刺激発生装置から高頻度で電気刺激を行う事で、機能障害を起こしている神経回路やネットワークを調整します。
(LCIG レボドパ・カルビドバ配合経腸用液療法)
内視鏡で胃瘻を作り、そこから小腸まで挿入したチューブを通じて持続的にL-ドパ製剤を投与する方法です。
(CSCI ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物持続皮下注療法)
体の中に入るとL-ドパ製剤に変わる薬剤を24時間持続的に皮下に投与します。
これは手術はせず、注射でできるお手軽さがあります。
リハビリ
運動療法や訓練はとても大切です。
動きが小さくなるパーキンソン病において、少しでも体を動かしていかねばなりません。
運動合併症
(ウェアリングオフ現象)
薬の効いている時間が短くなってしまい症状が変動する現象です。
(ジスキネジア)
薬が効きすぎて体がくねくねしてしまう現象です。
専門機関
日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)では、パーキンソン病療養指導士の認定制度を創設。
2025年の時点で1900名が登録されています。
パーキンソン病は、さまざまな領域の専門家が複数人で包括的に診ていく必要があるのです。
無血刺絡療法
脳外科医の長田裕先生が考案された無血刺絡療法により、パーキンソン病の症状が緩和されたという症例が同氏著書の「チクチク療法の臨床」に記載されています。
頭部への痛圧刺激により、減少したドパミンを排出させる効果が見られるそうです。
慢性急性の症状には、鍼や刺絡が効果的な場合もあります。
お辛い方は神楽坂東五軒町鍼灸整骨院へ。