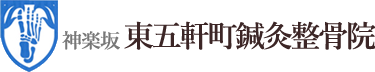60代男性 大腿部打撲の症例です。
症状
受傷当日にいらして頂き、拝見したところ大腿部の外側あたりに腫れと内出血がありました。
歩くと痛みがあり、膝の屈曲伸展が痛いという状態です。
処置と注意点
急性期の打撲の処置は、患部の冷却、干渉波などの物理療法、湿布、包帯圧迫固定などです。
受傷当日は、時間経過と共に腫れが強くなることがあります。
そのため、阻血にならぬよう少しだけ緩く固定します。
干渉波などの物理用法も効果的ですが、患部を避けて挟むように付けて弱い刺激に留めるべきです。
あえての無血刺絡
ですが今回、しっかり患者様に説明させて頂いた上で、無血刺絡を試みました。
刺激を加える箇所は、大腿部の腫れのあるところと傷口周辺と、腰部です。
大腿部を支配しているデルマトーム領域はL2、3、4です。
やはり、腫れがあるところや傷口近くはかなり刺激が強く感じる、腰はそうでもないとの事。
その後、座ったまま膝を曲げたり伸ばしたりしてもらったところ、先程よりも痛みが少ないとおっしゃってました。
経過
一度目の無血刺絡により、歩行時痛と膝の屈曲伸展動作(荷重なし)が3割程楽になりました。
二度目の時に拝見すると、腫れが前回よりも引いていて傷口周辺の筋肉がとても硬かったのですが少し柔らかくなってました。
痛みは、マックスの時と比べると今は半分くらいとおっしゃってました。
三度めは、腫れ痛み共にかなり楽で荷重ありの状態、すなわち立ったままの状態から膝を曲げてしゃがむという動作がほぼ痛みなくできるようになりました。
ライス処置
急性外傷に対する治療方針としてはライス処置が基本です。
ライスの処置とは、患部の安静、挙上、アイッシング、圧迫です。
そのそれぞれの英語の頭文字をとるとライスになるのです。
外傷と無血刺絡
無血刺絡療法の産みの親である脳神経外科医の長田先生は、ある時スキーで肘の骨折をしました。
ゲレンデから手術が出来る病院まで距離があり、天候の関係でなかなか動けなかったそうです。
そのような中、肘は大きく腫れあがり、ひどい内出血と激痛だったそうです。
耐え難い痛みの中でふと、患部に無血刺絡の痛圧刺激を加えたらどうなるかと思い、実行したそうです。
すると、痛みが大分楽になり日を追うごとに腫れと痛みが少なくなってきたそうです。
手術の前の日、手術後も痛圧刺激を行い、写真と記録も取っていて勉強会の時に見せてくれました。
骨折部が無血刺絡で治るわけではありません。
ですが、骨折による痛みは痛圧刺激で大分緩和されたのは大きな発見だったと仰っていました。
痛圧刺激と血流と除痛
「冷却や消炎鎮痛剤は一時的に血管を収縮させ痛みを紛らわせるだけ。」
「これでは逆に治りが遅くなる。」
「外傷の場合も無血刺絡や温めを行った方が治りが早い。」
と、長田先生はおっしゃいます。
外傷などで組織が傷むと、血管壁から内因性発痛物質が現れ局所に滞ります。
腫れがあるとさらに血流が悪くなり、発痛物質が出ると同時に滞ります。
そのため、痛圧刺激や温熱刺激で血管拡張させることで発痛物質を散らす事ができ、痛みが治まるという理論です。
注意点
ただし、そうはいっても急性の怪我で腫れがある状態の患部を温める事は僕にはできません。
以前勤めていた整形外科で、打撲によるかなりひどい腫れがアイッシングで大分引いたのを見たことがあったからです。
それに、腫れが強くなると壊死や重篤な後遺症に繋がる恐れがあり、医師もそれを懸念していたからです。
そのため急性の外傷に対しては、除痛目的で無血刺絡を行う事はあっても、温熱刺激は出来ないし、僕は患者様にも勧めないです。
慢性急性の症状には、鍼や刺絡が効果的な場合もあります。
お辛い方は神楽坂東五軒町鍼灸整骨院へ。