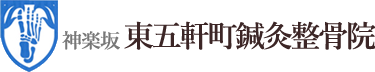今回の東洋医学シリーズは、東洋医学の疾病観についてです。
東洋医学では、天候の変化・過度の精神的な刺激・飲食の不摂生・過労のような体の内部の刺激や
天候などの外部の変化が原因となって体の不調が現れると考えられています。
その中でも、今回は天候の変化などの外部の変化である『外因』について考えていきます。
病の原因の一つ「外因」とは。
『外因』には、風・寒・暑・湿・燥・火の六つあります。
ではそれぞれ簡単に見ていきましょう。
「風」について。
風は四季のすべてにみられる気でです。
百病の長(すべての病の原因)とも言われる気です。
動きがあって色々なものに変化しやすいという特徴をもちます。
「寒」について。
主に冬の気です。
冬以外でも雨に濡れたり汗をかき風に当たったりすると、体に侵入し体を冷やします。
すると、陰陽のバランスが崩れ不調をきたすことになるのです。
「暑」について。
もう分かりますね。署は夏の主気です。
体を温めるだけでなく、盛夏には体の正気を消耗させ、現在で言う熱中症のような症状を引き起こさせる気です。
「湿」について。
梅雨や秋雨の頃の主気です。
湿は重く停滞する特徴があるので下半身をおかしやすいです。
特に関節に停滞すると痛みや腫れを引き起こします。
例えば、雨が降ると膝が痛い…という方がいますよね。
そのような方はこの「湿」が関係しているかもしれません。
また、五臓六腑の脾や胃をおかしやすい気なので、雨天時に食欲不振や消化不良をもたらすのもこの気が原因です。
「燥」について。
燥は秋の主気です。喉や鼻、皮膚を乾燥させる特徴があります。
「火」について。
「暑」以外の外熱をいい、体内の気や水分を消耗させる性質がある。また、出血させたり、腫瘍を形成したりします。
いかがでしたでしょうか。このように、東洋医学では季節や天候の変化が様々な影響をもたらしますし、体も外界の変化に対応し順応します。
しかし、天候が乱高下したり季節の変わり目などは、身体が外界の変化にうまく順応出来ずに体調を崩します。
このようにならないように、常日頃の体調管理が重要になってきます。
当院でも、中医学に基づいた鍼灸治療による全身調整も行っております。皆様のご来院をお待ちしております。