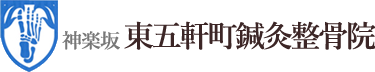報酬系に作用する糖。
糖質は生存に直結し、摂取するとドーパミンが出て脳の報酬系に作用します。
それすなわち、気を付けねば依存症になりやすいという事です。
そして、糖質をたくさん摂ると高血糖となり、言わずもがな糖尿病になるリスクが上がります。
人工甘味料。
人工甘味料は糖質ではありません。
ブドウ糖の数百倍もの甘みを脳が感じるだけのものです。
「数百倍の甘みを感じる」というと少し怖いですが、一応血糖値は上がらないとされています。
しかし、脳は明らかに強い甘さを感じるのに体は一切変化していないのは不気味です。
脳と身体における「感覚の乖離」が体内で不協和音と化し、後に何らかの体調変化に繋がる可能性はあると思います。
現に、人工甘味料はⅡ型糖尿病や一部の癌と関連があるともいいます。
Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Sante population-based cohort study Published: March 24, 2022 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950
インシュリンスパイク。
人工甘味料でなくとも、ジュースや甘ったるい果物の過剰摂取は気を付けねばなりません。
なぜなら、血糖値が跳ね上がるからです。
血糖値が高いと膵臓は大量のインシュリンを分泌します。
それにより血糖値を下げ過ぎてしまうため、今度はグルカゴンを出して血糖値を上げるのです。
この、乱高下する血糖値の事を「インシュリンスパイク」といいます。
空腹時にたくさんの食物を摂取してもインシュリンスパイクは起きやすいため、起床時すぐの飲食には注意が必要です。
インシュリンスパイクは、膵臓の他にも血管などの循環器系にも負荷が掛ります。
何事も極端はよくありません。
糖質はどこで吸収されるか?
甘いもの、すなわち糖質は胃で消化されて小腸で吸収されます。
糖質を口から摂取して小腸で吸収されて、血糖値に反映されるまでの時間は5分~10分程度です。
口腔粘膜からはほとんど吸収されません。
甘みを感じるのはどこ?
糖質を口に含んだ際に舌の味蕾がそれを受け止め、電気信号に変換して神経が脳に伝えます。
舌は場所によって支配神経が異なります。
前3分の2は顔面神経で、後ろ3分の1は舌咽神経です。舌の根元や喉は迷走神経です。
これらの神経は脳と直結しています。
甘みを感じたら即座に脳が認知する仕組みになっているのです。
なので先に甘みを感じても、実際に血糖値として反映されるのは後なのです。