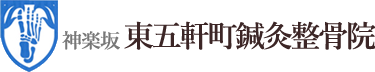肝臓はエネルギー代謝や有害物質の解毒などの働きがあります。
その他、ホルモンの調整、ビタミンの貯蔵、胆汁の生成なども行います。
これらのことから肝臓は、人体の化学工場とも言われています。
ALT。
Alanine Aminotransferaseの略で、肝臓に含まれる酵素です。
ALTは細胞がダメージを受けて壊れると血液中に放出されます。
そのため、肝細胞のダメージが大きい程、数値が高くなるのです。
ALTの数値
30以下→正常
40以下→軽度異常
50以下→要再検査、生活改善
51以上→要精密検査、治療
脂肪肝。
ALTが高くなる理由の一つに、脂肪肝があります。
脂肪があると、肝臓をエコーで見た時に白く写ります。
痩せていても脂肪肝になっている方もいます。
脂肪は肝臓の細胞に溜まります。
すると細胞が膨らみ始め過剰に増えると破裂するのです。
これは肝細胞の死と言えます。
つまり、多くの脂肪が蓄積されるとそれだけ肝細胞が死に、肝機能が低下します。
肝臓は取り込んだエネルギーを栄養に変える働きがあります。
この働きが弱ることで、身体が疲れやすくなるのです。
脂肪肝は、生活習慣と食事が大きく関係しています。
食事にはなるべく多くの「色」を取り入れねばなりません。
ご飯は白、お肉は茶色、野菜は赤や緑という具合です。
脂肪肝の方の食事は茶色中心である事が多いです。
色味が少ない食事は炭水化物や脂質など栄養が偏りがちです。よって、肝臓に脂肪が溜まりやすいのです。
食事には様々な色を取り入れる事が肝要です。
アルコールと肝臓。
睡眠中、肝臓はアルコールや老廃物など有害な物質を無毒化しています。
例えば、500mlのビールに含まれるアルコールは20gです。これを肝臓が無毒化するのに4〜5時間かかります。
ワイン(度数12%)はグラス2杯でアルコール24g。
これは5〜6時間肝臓が休みなく働きっぱなしになるのです。
ただし、これは正常な肝臓の代謝時間です。
上記のような脂肪肝など、傷ついて機能低下した肝臓にはもっと負荷がかかります。
弱った肝臓は、本来の働きのエネルギー精製で精一杯です。そのため、アルコールを分解する余裕はないのです。
夜遅い時間の夕食はよくありません。
遅い時間は人体の基礎代謝が低下します。
この状態で食事をすると、摂取したエネルギーが使われません。そのエネルギーは中性脂肪として肝臓に蓄積されるのです。
その働きのために肝臓は夜通し働き続けるので、寝ても疲労が取れないのです。
そのため、夕食はあまり食べないようにして朝食に重点を置くべきです。
睡眠。
肝臓は身体を横にして休んでいる時に1番働くのです。
睡眠時間が少ないと、肝臓の働く時間が少なくなります。限られた時間で働かねばならないのでフル稼働となり、強い負荷がかかります。
肝臓に良くない行動。
①食事の彩りが少ない。
②毎晩、晩酌している。
③夕食が10時より遅い。
④睡眠時間が6時間以下。
2つ以上当てはまると肝機能に差し障ります。