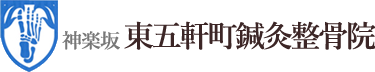夏に胃の不調を感じる人は国民のうち約4割いるとされています。
一つは自律神経の乱れによるもの。二つめは血中のナトリウム不足。3つめは胃腸の冷えです。
自律神経と胃腸の関係。
自律神経の乱れは、近年夏が暑すぎる事で身体も神経もだらけやすくなります。これは副交感神経というリラックスの神経が優位になります。
「だらける」理由は、あまり動かないようにして、身体が熱くならないようにしているのてます。これも恒常性を維持するための立派な反応です。
リラックスしていると胃腸の動きが良くなりますが、あまりにもリラックスしすぎると胃酸が多く出たり、胃腸の蠕動運動が促進して下痢になったり胃が痛くなります。
さらに、外は暑いですが、スーパーなど屋内はどこにいっても寒いくらい冷房が効いています。
これは逆に熱を逃さないように交感神経が優位になって血管が収縮します。身体と神経は緊急時を想定するので当然、胃腸の動きも悪くなります。
暑いと寒いが繰り返される事で自律神経が乱れて胃腸の不調を招くのです。
胃腸だけでなく、夜も暑くて寝苦しいです。
かといって冷房が寒かったり喉が乾燥したりします。結果、寝不足になりやすいのです。
ナトリウムの不足。電解質異常と夏。
夏場に血中ナトリウムの濃度が低くなりがちなのはある意味で必然です。
なぜなら、汗をかくいてナトリウムが外にでていくからです。そして、水をたくさん飲むと血中ナトリウム濃度がうすくなります。
細胞が元気で、身体を良い状態に保つ日はナトリウムやカリウムなどの電解質が絶対に必要です。もしもそれらが少なくなると身体が正しく機能しなくなり、内臓や筋肉に至るまで多大な異常ををきたす事になります。
夏は知らない間に脱水、電解質が失われがちです。意識的に水分の他に塩っけのあるものを摂らねばなりません。
食中毒と夏。
を招くもう一つの理由は食中毒です。アニサキスやカンピロバクター、サルモネラ菌などは6から8月に多い傾向にあります。
温度が高くて食材が痛みやすかったり、暑いから刺身を食べがちになり寄生虫がついていたりなんてこともあります。生卵や肉、魚、火を通さず常温保管したものなど気をつけて下さい。
家庭での食中毒を防止するには、①つけない、②増やさない、③やっつける、この三つが大切です。
手についた細菌を食材や食器につけないように、そして細菌を増やさないように適切に食材を処理するか取っておかずに食べ切ってしまう、最後になるべくしっかり火を通して殺菌するる事が肝要という意味です。
身体は冷やしても腹は冷やすべからず。
胃腸の冷えは、冷房と薄着、冷たい飲み物、アイスやビールなどにより身体が冷えてしまいます。
冷たいものはゆっくり食べる、風呂に入る、腹巻きをするなどの対策がおすすめです。