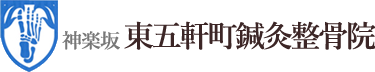真性多血症とは、赤血球が増えすぎて血液がドロドロして血の巡りが悪くなってしまうという病です。放っておくと急性白血病に移行することもあります。
合併症や疫学
多血症は年間800人ほどの人が発症しています。
しかし、自覚症状が少ないため気づいていない人も多いです。好発年齢は60から65歳です。上述の通り、赤血球が増えて血液がドロドロになるため、脳梗塞や心筋梗塞など血栓症由来の病気を発症しやすいのです。
多血症の症状
多血症の初期は自覚症状が乏しいですが、進行してくると頭痛、めまい、赤ら顔、入浴後の皮膚の痒み、視覚や視野の異常、感覚異常などが出てきます。
では、どのように発見、診断が下るかというと会社などの健康診断で行う血液検査にて異常が見つかる事が多いです。その後、専門病院で精密検査を受けて診断に至ります。主に、ヘモグロビンの値、ヘマトクリットの値を見ます。
JAK2遺伝子
ほぼ全ての多血症の方は血液検査により、JAK2遺伝子に異常がみられています。これは、赤血球の量を管理しているホルモンに影響を与えて、赤血球を増やすアクセルのみが踏まれてブレーキがかからない状態になるのです。
なぜJAK2遺伝子に異常が起きるのかはまだよくわかっていません。
治療方針
赤血球が多いため、瀉血により血液を抜く事が基本的な治療方針となります。一回に注射器で400cc近くの血液を取って捨てます。ヘマトクリット値45%未満を目指します。
血栓症を防ぐために低用量アスピリンを服用します。これは血小板の凝集を防ぐため、簡単にいうと血液が固まりにくくなるのです。
多血症は元々、赤血球が作られる骨髄での病変です。骨髄に変異が生じた場合、血液の癌と言われる白血病に移行する可能性もあります。そのため、抗がん剤の一種が治療薬として用いられる場合もあります。ヒドロキシウレアといいますが、これを飲むと比較的速やかにヘマトクリット値が理想的な数値になるそうです。
JAK2遺伝子を働かせないためのJAK阻害薬もあります。
ロペグインターフェロンα2といいます。
この薬は、上記のヒドロキシウレアがあまり功をなさない場合に用いられます。ロペグインターフェロンα2は、JAK 2遺伝子を抑制すると同時に腫瘍細胞を減らす、いわば抗がん剤の役割も兼ねるといいます。
副反応と自己注射
インターフェロン系の薬は、インフルエンザワクチン接種後のような副作用が起こる事があります。具体的には、発熱、寒気、甲状腺の異常などです。しかしロペグインターフェロンα2はそれが少ないとされています。
そしてこれは医師と相談の上で自己注射、すなわち頻繁に通院せずある程度家で治療をする事も可能だそうです。
刺絡と瀉血の違い
刺絡療法は古来より鍼法の一つです。細絡という毛細血管に鍼を刺して滞った血液を数㏄程出して気や血の巡りを良くしたり、ツボ刺激と痛圧刺激を通じて自律神経を整えるのが目的です。
そのため、施術を行う理由、狙う部位、狙う血管、出血量、用いる道具などが明らかに異なります。無論、瀉血は医療行為であり注射針を使うので鍼灸師はできません。刺絡でも出血はしますが、出てもせいぜい50㏄程度です。多血症の場合は必ず病院で適切な治療を受けて下さい。