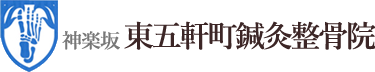なぜ魚のお刺身は種類によって色が違うのでしょう?
人間の身体とはあまり関係ありませんが、そこに魚類の生存戦略が見えてきます。
長く泳ぐには大量の酸素が必要
マグロの背中部分の筋肉は赤く、お腹側は脂肪を多く含んでいるので白いです。
マグロは長距離を時速70キロくらいで休みなく動いている高速回遊魚です。
なぜ休みなく泳いでいるかというと「ラム換水法」といって、泳がないと呼吸ができない仕組みだからです。
休みなく動き続けるには、常に酸素を筋肉に送り込まなければなりません。
酸素を送り込んでエネルギーに変換して筋持久力を高めるのです。
そのために役立つのがミオグロビンです。
ミオグロビンと酸素
血液中のヘモグロビンが酸素を筋肉に運び、筋肉内のミオグロビンが酸素と結びつきます。
これは魚だけでなく人間も同じです。
ミオグロビンは酸素のストックのようなものです。
必要な時に酸素をエネルギーに変換して筋肉がそれを使うのです。
よって、ミオグロビンが多い程筋持久力は高くなります。
なぜマグロの刺身(背中の部分)は赤いのか
上記のミオグロビンは鉄を含んでいます。
ミオグロビン内の鉄が酸素にくっ付くと赤く見えるようになります。
なので、より多くの酸素を必要とする筋肉にはミオグロビン(鉄)が多く、その酸素と鉄が結合すると赤くなります。
筋肉内のミオグロビン、鉄、酸素が多ければ多い程その筋肉は赤色になるのです。
白身魚はなぜ白い
その理由は、あまり動かないためミオグロビンが必要ないからです。
白身魚は「エラ呼吸」です。
エラ呼吸とは、エラを通じて水分中の酸素を無数の毛細血管内に吸収して呼吸する方法です。
一方、ラム換水法のマグロはエラが退化しているか、もしくは機能が不十分です。
そのため、自らが泳いだ際に発生する水流がなくては酸素をエラから得る事が出来ないのです。
そういった意味では白身魚の方が、性質や進化の歴史の上で新しい存在なのかもしれません。
鮭はなぜサーモンピンクなのか?
では、鮭の色はどうでしょう。
結論から言うと、あの色はアスタキサンチンによるものです。
アスタキサンチンを含むエビやオキアミ、カニなどを捕食するためにオレンジ色の色素が吸収されてサーモンピンクとなるのです。
鮭は本来は白身魚で、エラ呼吸です。
ではなぜアスタキサンチンを選択的に摂取するのでしょうか?
川を昇るための莫大なエネルギーが必要
鮭は川で生まれます。
その後、海に流れて大人になり、もう一度生まれた川に帰って産卵します。
言わずもがな、川と海では川の方が高い位置にあります。
つまり、鮭が海から川に帰るには、川の流れに逆らって泳いでいかねばならないのです。
それにはスタミナ、パワー、疲労を軽減して回復するシステムなどが必要になります。
そのために必要なのがアスタキサンチンなのです。
アスタキサンチンには、抗酸化作用(筋肉や細胞を守る働き)、紫外線からの保護、激しい運動で生じる活性酸素を除去する作用があります。
養殖の鮭
では、養殖の鮭はどうでしょうか?
養殖ならば川を昇らないため、アスタキサンチンは必要ありません。
そのままにしておくと、必然的に鮭の色は白くなります。
しかし白色の鮭では食欲がでないという事で、養殖の場合は餌の中にアスタキサンチンを添加しているそうです。
色は同じようにできても、天然と養殖の鮭とでは筋肉の付き方が違うのは言うまでもありません。
そこに、味わいや触感、希少性の妙味が出てくるのでしょう。
魚はすごい
魚類の中でも、それぞれに特徴や特性があります。
「どうすれば己を最適化できるか」そしてそのためには「何が必要か」を、各々が自覚してそれを摂取しているというのは凄いなと思いました。
アスタキサンチンやミオグロビンなど、魚らは一体誰に教わるのか、はたまたDNAに刷り込まれているのか…。
いずれにしても、今の生存戦略が彼らにとってベターでベストなのでしょう。