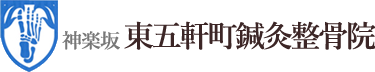秋は紅葉と落葉の季節だ。
いつも通る道にもそれなりに枯れ葉が落ちている。
近隣マンションの清掃員の方が毎朝、かがみながらホウキで落ち葉をかたずけているのを見る。
清掃の仕事は比較的、年配の方が多い。
自分も仕事柄、中腰姿勢が多いため腰の負担と疲労に関しては精通している。
その観点から見ると、清掃員の方は腰を傷めないかいささか心配になる。
特に寒い時期だから尚更だ。
毎日降り積もる落ち葉
通行人からしたら歩道の落葉は風情を感じる秋の象徴だ。
「落ち葉が嫌い」という方は珍しいのではないかと思う。
だが、もし自分が清掃員ならば落ち葉が憎くてしょうがないだろう。
なぜならば、掃いても掃いてもまた降り積もるからだ。
昨日の労働を、いや、今朝の労働をあざ笑うかの如く、数時間後にはまた降り積もっている。
その落ち葉を毎回、腰の疲労と負担、時間と労力を犠牲にして片づけなくてはならない。
申し訳ないが、僕ならばいっそ木を切ってしまうかもしれない(笑)
「ちりを払う」
以前、お寺の住職がテレビでこんな話をしていた。
仏陀には幾人か弟子がいて、その中に須梨槃特(しゅりはんどく)がいた。
須梨槃特は仏陀の事が大好きで、忠誠心があり、真面目でとても熱心な人物だ。
しかし記憶力と頭の働きが壊滅的に悪く、全くお経が覚えられず、何も仕事が出来なかったそうだ。
須梨槃特はなんとかして仏陀の役に立ちたいと思い、何か仕事を与えてくれと言った。
何をお願いしてもすぐに忘れてしまう須梨槃特に対して仏陀はある日、超単純で解りやすい言葉で仕事を命じた。
それが「ちりを払え」だった。
それからというもの、須梨槃特は「ちりを払え、ちりを払え」と呟きながら来る日も来る日も仏陀の家の周りのちりを払った。
そしてある時、気付いた。
「昨日、というかさっき完璧に綺麗にしたのに、もうちりがあるではないか」と。
払っても払ってもちりは積もる。
それでも「ちりを払え、ちりを払え…」と呟きながら毎日毎日無我夢中でちりを払い続けて、またある時、気付いた。
須梨槃特は「ちりはあって当たり前」と思うに至ったのだ。
ちりはあって当たり前
これは大きな気づきであり悟りだった。
後に須梨槃特は、修行により悟りを完成させた人物を意味する「阿羅漢果」になる。
さて、この「ちりはあって当たり前理論」は哲学でもある。
哲学から実践的な学びや戦略を得る事をプラグマティズムという。
「ちりはあって当たり前」から何が学び取れるだろうか?
情報、感情、雑念により自滅する現代人
現代社会では自ら命を絶ってしまったり、精神不安定からノイローゼとなったり、脳が変性を来たして依存症になったりと、人生が壊れるルートが複数ある。
病気、事故、加害を除くと、これらははっきり言って「自滅」なのだ。
自分で勝手に人生を壊していると言っても過言ではない。
自滅に追い込まれる原因は主に、情報、感情、雑念だ。
SNSでは、Instagramユーザーが一番自殺率が高いらしい。
※FacebookはInstagramが一部のティーンに与える被害を軽視 – テックニュースブリーフィング – WSJポッドキャストより抜粋
他人のラグジュアリーな私生活、不安やヘイトを煽る記事、偽動画、目障りな広告などの情報を見る事で感情が乱れ、サイトのアルゴリズムで脳が変性し依存を起こす。
はたまた、LINEなどのアプリやグループを介したメッセージのやり取りでの齟齬や仲間外れ、いじめなど。
結局、不完全な生き物である人類同士が不完全なツールとシステムを造り、それを使っているからトラブルにもなるし、制御しきれないのだ。
そして脳も上手く情報を処理できていない。
なぜなら、我々人類の脳の発達よりもITの発達と進化の方が速く、我々の脳はそれについていけていないからだ。
通知を見ずにいられない習性
なぜ現代人はスマホの通知を見る?
お知らせ、おすすめ、メッセージ、最新情報などを日に何度も何度も。
これは、生き残るために情報が必要だった原始時代からの習性で、「何か生存に役立つのではないか」という本能が働き、「おしらせ」が気になってしかたがないらしいのだ。
※アンディシュハンセン著書 スマホ脳より
ここから解るように現代人は、今でも原始時代の脳から大してアップグレードがなされていないのだ。
そこに、好むと好まざると膨大な情報が日々脳に流れ込んでくる。
まさに「払っても払ってもチリは溜る」のだ。
感情、情報、雑念はあって当たり前
「ちりはあって当たり前」の意味するところの一つとして、「ちり」は雑念と負の感情、という解釈がある。
つまりどんなに頑張って修行しても、怠惰、嫉妬、憎しみ、欲望などの感情や雑念は人間である以上、必然的に想起しうるという事。
それを踏まえた上でどう生きるか?という事が真髄なのだろう。
ただ、須梨槃特の時代から時が進んだ現代では、自分の感情という「ちり」の他、膨大な情報という「ちり」とも向き合わねばならない。
IT、SNSの倫理と品格の是非を問う前に「ちりはあって当たり前」という前提をもう一度考えるべきだと思う。
現代において、ちり(ゴミ)みたいな情報はあって当たり前なのだ。
消しても消しても、見ないようにしても次々と湧いてくる。
ちりの中には価値のあるものもあるが、有害なものもある。
今こうしている間にも、ちりは生み出されて降り積もっている。
無価値なゴミにいちいち感情が揺さぶられたり、意識が分散されていてはいけない。
理解と認識、そして強い精神力が必要だ。
…無論、このブログも「ちり」の一つであることはいうまでもない(笑)