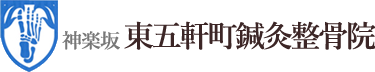微小循環障害が起きて瘀血状態になると、血液の粘着度は亢進して流れにくく血小板機能も亢進して血液凝固が起きやすくなります。これは微小循環障害における血流の停止(ステーシス)に近い状態です。これが更に進むと血液は凝固して血栓が形成されて梗塞を起こします。
血液と血流が正常な状態において赤血球は、組織に酸素や栄養素を与えやすくするため、あまり赤血球同士がくっかないよう隙間を開けて血管内を流れるという性質があります。しかし、瘀血状態になると赤血球はお互いにくっつき数珠状に連なって血管内を流れるようになります。
この状態の事を、「血管内赤血球集合」、「泥状現象」、「スラッジ現象」などといわれます。これらは高脂血書症、動脈硬化、脳梗塞、脳出血などにもつながる前段階とも言えます。
瘀血、または微少循環障害の原因としては、生活における不摂生以外にも精神的な緊張が昂ることで自律神経に影響を与えて交感神経が優位になることで血液の凝固や凝集に関与するとも考えられています。ストレスも瘀血に関与する大きな要因の一つなのです。
瘀血から血栓が生じて下肢に影響を与えればエコノミー症候群、心臓ならば心筋梗塞、脳ならば脳梗塞など、瘀血は人体のあらゆる箇所、臓器に悪い影響を及ぼします。臓器だけではなく、なんらかの皮膚病に関しても慢性化すると必ずそこには瘀血が伴います。これは皮膚を養う血管の血流の流れが障害されて皮膚病の回復が悪くなる事に基づいています。
そして当たり前の事ですが、正常な血液は血管内を巡行しています。だからこそ全身に血液を介して栄養や酸素を届ける事ができているのです。しかし、血管がやぶらてその血液が脈外に出た場合にはこれも瘀血と考えます。具体的には外傷、紫斑、打ち身、捻挫などによる内出血、鼻血、吐血、脳内出血などがこれにあたります。これらな血管外に漏れ出て正常な血液としての機能をしなくなった病理産物、すなわち瘀血ととらえるのです。
微少循環障害により起きる血管内の現象について以下に記します。
①ステーシス(血流の停止)
ステーシスとは顕微鏡下に微少循環系を熱したり冷やしたりして物理的に刺激した時に、毛細血管、中心毛細血管、細静脈に起こる血流停止状態をいいます。
②スラッジ現象(血管内赤血球集合)
赤血球がくっつき合って流れるようになるので血液は血管内を流れにくくなります。この状態になると赤血球の表面積が減少するので組織に酸素を運ぶ赤血球としても機能は低下します。
③血液が粘着性を帯びて血管内を流れにくくなる(血液粘度の亢進)
血管内の血流の鬱滞は血液粘着度の増加、血流促進の緩慢、赤血球の凝集性の亢進、血小板の凝集などによるものです。この状態は「血液がネバネバ」して流れが悪く、赤血球はお互いに凝固して血栓となって血管内をつまらせてしまいます。
④さらに進行すると血栓症や梗塞になる
血管内に凝固した血液が詰まり、血栓や梗塞を起こしてその先の詰まった臓器の機能障害を起こすのです。
⑤出血へと進行する
血液が血管外に漏れるのも瘀血の一つの病的状態です。脳の血管から出血すると脳出血になります。皮膚の血管から漏れるとそれは皮下出血となるのです。
さて、現代医学において瘀血の治療方針は、血液をサラサラにする事です。ワーファリンなどの薬物療法、または静脈瘤や動脈硬化が酷い場合はステント留置や人工血管置換などの外科的処置を行う場合もあるでしょう。
そこに行き着く前の段階で、瘀血形成がなされる前になんらかの処置を取り、瘀血を予防せなばなりません。無論、刺絡療法を受けたり漢方薬を飲む前に予防するのです。そのためには、規則正しい生活と、適度な運動、筋トレ、バランスの良い食事、身体を温める事と自律神経のバランスを保つ事です。