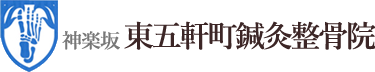「生きる力になる禅語」という本は非常に興味深かった。
臨済宗円覚寺派管長 横田南嶺さんと、天台宗圓融寺住職 阿純章さんとの対話形式で「禅」の事が幅広く書かれている。
いくつか学びに繋がった事柄を自分の考えを交えながら紹介する。
「平常心について」
本来、平常心は「びょうじょうしん」と読むらしい。
平常心とはピアノの発表会などで緊張する時に唱えるおまじないのように思っていた。
しかし「禅」でいうところの平常心はちょっとニュアンスが違う。
心拍などのバイタルではなく「人格」に近い。
人間には誰しも二面性がある。
「なまけている自分としっかりしている自分。」
「時として悪魔、時として天使。」
などというのが誰しもあるはずだ。
「どんな時でも変わらず丁寧に振る舞い、オンでもオフでも変わらない生き方をする。」
これこそがいつも変わらない「平常心」という事らしい。
いつも変わらずに良い状態でいる。
「そんなの無理だ」という人も多いと思う。
これは相当修業がいるし、一朝一夕にはできない。
逆に意識的にオンとオフを使い分け、二重人格のような人もいるだろう。
だが、出来る事ならはなるべく平らにするよう実践した方がよいと思う。
なぜなら「人格の使い分け」は、自己矛盾が生じていずれどこかで苦しむ。
自分の「良い人レベル兼しっかりしてるレベル」をDからSSであらわすとする。
この場合、S+のように極端に良すぎる状態を常とするのは負担が大きくて大変だ。
なので目標設定としてまずはB+とかAあたりが標準になるよう始めるとよいのではないか。
煩悩の使い方。
108の煩悩という言葉は誰しもどこかで聞いた事があるだろう。
多くの妄念、欲望が人間の心に纏わりついているという意味だ。
一般には煩悩は良くないものと捉えられているが、煩悩を消す事は不可能に近い。
これを無くすために修業するという宗派もあるが、逆に煩悩があって然るべきとする宗派もある。
この本には「世の為人の為に煩悩を使うならば良いのではないか」と書いてあった。
「もっとこれがしたい」という意欲が世の為人の為になるならば、良い循環といえるだろう。「日々、自己を高めるために意欲を持って努力し、私利私欲ではなく世の為人の為に煩悩を使う。」書くのは簡単だ。
実践するのは難しいが、少しずつ頑張っていこうと思う。
この世の真理⁉禅問答。
「禅問答」というのがある。
禅の老師からの哲学的な問いに対して弟子が答えるというもの。
これがまた難しい。
なぜなら、科学や社会学などの知識教養が全く通用しないからだ。
文明がもたらした専門知識ではく、真に肚で理解するようなそんな感じの問いなのだ。
例えば「命の長さ」とは?
これに対して弟子たちがそれなりの答えを言うのだが老師はすべて否定する。
それは真の理が見えていないからだ。
奪って奪って奪い尽くす。
そして、とかく解ってない者に対しては否定して否定して、奪って奪って奪い尽くすというのだ。「奪う」とは?
例えば、弟子が数学の偉い先生だとしたら、与えられた問いに対して自分の強みである数学を使うだろう。
だが、「数学では解けない」と「数学の力」を無力化させられてしまう。
そして同時に「権威性」も奪われてしまう。
禅問答では偉くても若くても貧乏でも金持ちでも頭がよくても関係ないのだ。
考えて、答えて、否定され、を何日も何日も続ける。
そうしているうちに、頭の中にある全ての可能性が枯渇し真っ白になる。
そればかりか来る日も来る日も否定され自分自身の存在が透明になっていくような、そんな感覚になるという。
すべてを考え尽くした後に何が残ったか?そこで初めて「真の自分」というのが垣間見れるらしい。
そして、ふと無心になった時に最適解が自ずと降りてくるものだ。
これこそが悟った瞬間なのだろう。
臨床と悟り。
これは臨床に通じるものがある。
病院で異常なし、あるいは原因不明といわれる難治性の症状を抱える患者様が当院に来院された時。
鍼灸院において、病院と違う視点であらゆる事を考えてアプローチしても改善がみられない。
このい、「どうしても改善しない」という時に強く無力感を感じる。
しかし、あらゆることを考え尽くして無になった時、自然に沸き上がる答えというか思いが見えてくるという感覚は経験したことがある。
そして、何度も解決策を探して探して探し尽くす事で、脳内の見えないフィールドが前より少し広がったようなそんな感覚もある。
無論、その「悟り」みたいな脳の力ですべて解決するわけではないし、必ず答えが得られるわけでもない。
結局、力及ばずで改善しない事もある。
だが、そこで見つけた結論はシンプルでなぜか腑に落ちる事が多い。
一無為の真人。
誰もが「一無為の真人」を心の中に持っている、というかいるという。
これは簡単にいうと、一切何も纏っていないという意味だ。
高級な衣、肩書、見栄え、年収、損得などに全く捉われない、「真の心」が誰しもあるという事らしい。
これも解る気がする。
特に人様の痛みと向き合う医療関係の仕事の人は解るのではないか。
何かのタイミングで、潜在的にも顕在的にも理屈や損得、保身などの感情や思考が一切除外されてしまう瞬間がある。
ただ相手の事だけを思ってほぼ全自動で行動している状態。
自然と手と胸が熱くなるような経験が医療関係の人なら一度はあるはずだ。
恐らくこれが一無為の真人の片鱗なのかもしれない。
無我とは?
「何もない」という事、「隔たり」がない事を無我という。
なぜあらゆるトラブルや事故が起きるのか?
それは、そこに「隔たり」があるからだ。
これは究極の考えだが、例えば岩にぶつかって肩を怪我したならば、「自分も同じ岩の一部」ならば怪我しない(笑)
自分とその物質との間に隔たりがあるがゆえに怪我をする。夏が暑くて困るならば自分も夏の暑さになればいい。そうすれば暑くない(笑)…ちょっと違うかもしれないけど、要はそうゆう事だ。
無我の概念は人とのコミュニケーションに置き換えてみると解りやすいと僕は思った。
例えば、夫婦喧嘩などなぜ人は喧嘩をするのか?
それは「自分が相手ではないから」だ。
その証拠に、相手がいなくて一人きりであれば絶対喧嘩にならない。
相手がAと思うのに自分はBと思うから意見の相違で喧嘩になるのだ。
ここで自分と相手の隔たりを無くす、つまり相手と一心同体になれば理屈上はトラブルにならない。
「自分しかいない」もしくは「自分がいなければ」トラブルにならない。
最後に。
この本に書かれている大切な事はまだまだ色々あるが、とりあえずこのくらいにしておく。
それに、禅に関する本はまだこの一冊しか読んだことがない。
たった一冊では禅の何たるかは禅の片鱗の「へ」の字くらいしか分からないだろう。
機会があればまた別の本を読んで少しでも理解を深めようと思う。