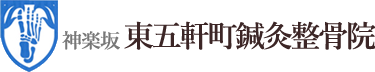足底腱膜炎の場合は足底部やS2、L5の神経支配領域内をくまなく診る必要がある。
すなわち、患部から離れた下肢全体という事だ。
離れた箇所に原因がある可能性
足裏のみならず、下肢全体をとらえて施術することで楽になるケースが多い。
それらを行っても一向に症状が変化しない時は足の横アーチを見るのもひとつ。
アーチが高すぎないか、逆に低すぎないかを見る。
足趾の筋腱、骨間筋
そして足趾の筋腱、骨間筋のストレッチをかけて見る。
足趾を扇状に広げてみてこの状態で痛む動きをしてみてもらうのだ。
すると、ふくらはぎや後脛骨筋の筋硬結部位を押えていた時よりも痛みが軽減する場合がある。
負担を背負うシステム
沢山歩いたり、立ちっぱなしだったりするとまずは足裏の割と表層の足底筋膜部に負担が掛かる。その後、足底筋膜部だけでは負担を背負いきれなくなると、下腿の筋がそれを負う。
下腿で背負いきれなくなると大腿が負担を担う。
このように、末端が受けて処理しきれない負荷を上の大きな組織が請け負うシステムがあるのだ。
しかし、負担請負システムが一巡しても負荷が掛り続けると、脆弱部にダメージが加わり始める。
それは末端の弱い組織や、筋腱移行部、古傷など、たとえ大きな筋でもダメージは蓄積する。
いつしか、リカバリーが追い付かなくなった時に、組織が傷ついて「症状」がでるのだ。
痛まないためには
身体の癖は誰しもあるが、一部分に負荷が掛るような不自然な癖はなるべく直した方が良い。
仕事や趣味で、どうしても負荷が掛る場合もあるが避けれるものは避けた方が良い。
その他、使った後は温める事が肝要だ。
おなじ筋肉を多く使うと、血の巡りが悪くなる。
それにより、痛みが出やすくなると同時に、細胞の代謝が落ちて組織が痛みやすくなるのだ。
よって、使った後は温めて血流を良くして代謝を促す必要がある。
レスト、負荷からの離脱、温めを覚えて頂きたい。
急性症状、慢性症状には鍼や刺絡が効果的な場合がある。
お辛い方は是非、神楽坂東五軒町鍼灸整骨院へ。