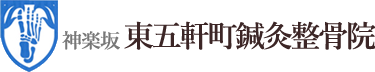皆様こんにちは。
今日は、鍼灸理論シリーズから鍼灸治療の禁忌について書いていきます。
鍼灸治療とは。
まずは考え方についてです。
鍼による機械的刺激あるいは温熱刺激を与え、効果的な生体反応を引き起こし、保護、疾病の予防、治療などに用いられます。
刺激による生体反応は施術した部位だけでなく、中枢神経系の様々な部位を介して遠隔部にも反応が生じます。
その結果、鎮痛、自律神経系、内分泌の調節による全身的な影響、血流の調節や免疫機能の変化などが生じ、様々な症状や疾患が改善すると考えられています。
このことから、鍼灸治療は機能的疾患に対して最も効果を上げる事が出来るといえます。※鍼灸理論の教科書から抜粋。
禁忌。
WHOの基準に基づく、主な鍼灸の適応症の表があります。
書くと長くなってしまうのでまたの機会にでも書きます。
さて、ここで本題の鍼灸治療の禁忌についてです。
鍼がだめな部位。
刺鍼を避ける部位として、新生児の大泉門、外生殖器、臍部、眼球、急性炎症部位、などです。
また、臓器に対しての刺鍼も禁忌です。
具体的にいうと、肺、胸膜、心臓、腎臓、脊髄、延髄、中枢神経系、大血管などです。
灸がだめな部位。
顔面部や化膿を起こしやすい部位、浅層に大血管がある部位、皮膚病の患部などへの直接灸は避けねばなりません。
生体反応を応用したものが鍼灸治療な病態や症状の改善を目的に鍼灸治療が行われてきたために疾患名で絶対的な禁忌を決めるのは難しいです。
一般的な禁忌を以下に示します。
①安静が必要な場合
②刺激を加えることで有害作用を起こす場合
③免疫能が低下し、感染危険が高い場合
などは施術を避けるべきと考えられています。
WHOのガイドライン。
妊娠(陣痛を誘発する可能性、流産誘発する可能性がある)
救急事態もしくは手術必要とする場合。
悪性腫瘍(腫瘍への直接刺激は避ける)
出血性の疾患
と、書かれています。