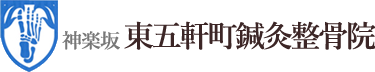こんにちは。今日のツボシリーズは、『多汗』についてです。
特に夏場は汗についてお悩みになっておられる方も多いのではないでしょうか。
服装にも影響が及びますし、汗をかいてそのままにしていると風邪をひいてしまうこともあります。
また、緊張すると汗が止まらない…という方もいるでしょう。
一概に『汗』とは言っても、西洋医学的にも、東洋医学的にも様々な原因が考えられます。
そこで今回は東洋医学的に『汗』とはどのようなものとして捉えられているのかを見ていきましょう。
東洋医学的な「汗」とは。
多汗症の事を東洋医学的には『汗証』といいます。
この汗証には『自汗』『盗汗』『脱汗』という三種類のタイプの汗証があります。
『自汗』は時々汗が出て、動くともっと大量にでるものをいいます。
『盗汗』は睡眠中に出る汗です。これは、起きると止まります。
『脱汗』は大汗が止まらず、油のような汗が出るものをいいます。
また、この様々な汗証は毛穴の開閉の機能がうまく働かないことによって起きるとされています。
今回は『自汗』と『盗汗』について原因別に特徴と使うツボの一例を見ていきましょう。
①風による自汗。
風邪により皮膚に潤いや栄養がいきわたらなくなることが原因です。
それにより、開閉機能が異常を起こすタイプの『自汗』の場合です。
特徴/風に当たると悪化する・体が重だるい・悪寒や発熱が起きる・不眠や頭重感がある
ツボ/風門、風池、合谷、列缺
②肺気虚による自汗。
皮膚を栄養したり、潤いを与えている肺気が弱っているタイプの『自汗』の場合です。
特徴/風に当たると悪化する・息切れがある・寒がりである・顔色が悪い
ツボ/肺兪、太淵、足三里、中府
③疲労や出血による盗汗。
心身の疲労や出血が原因です。
それにより、汗を貯蔵する役割がある心血が消耗して汗が漏れ出てしまうタイプの『盗汗』です。
特徴/動悸や息切れがある・不眠や夢が多い・精神疲労がある・顔色がさえない
ツボ/神門、内関、膈兪、合谷
④陰陽バランス不安定による盗汗。
何らかの原因で陰分が不足することが原因です。
それにより、陰陽のバランスが崩れ熱が発生し汗が漏れ出てしまうタイプの『盗汗』です。
特徴/夕方に熱が出る・夜に手や足が火照る・痩せる・月経不順(女性)・夢精(男性)
ツボ/神門、大陵、太谿、太衝
いかがでしたでしょうか。色々な汗があるのがお分かりいただけましたでしょうか。
私たちは逆に、お身体の状態を把握するために問診などで汗の状態をお聞きすることもあります。
汗が健康のバロメーター。
そのくらい汗とは東洋医学ではお身体の状態を診るバロメーターになります。
最近、汗のかき方が変わってきたという方、お身体の状態が変化してきているのかもしれません。大病につながる前に食生活や生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。
具体的にご質問があるという方、お身体を診てほしいという方、是非当院にいらして下さい。