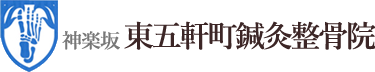こんにちは。今日の東洋医学シリーズは「五臓六腑」についてです。
ビールをグイッと飲んだ時「五臓六腑に沁みわたる〜」なんていう使い方もされる「五臓六腑」という言葉。皆さんは「五臓六腑」という言葉の意味をご存知でしょうか。
五臓六腑とは。
この「五臓六腑に沁みわたる」ということわざは、腹の底まで沁みとおることをいいます。
五臓六腑とは、五つの内臓と六つの腹わたのことです。
五臓とは、肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓の五つ。
六腑とは、胆、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦の六つです。
このことついては、中国最古の医学書である「黄帝内経」に書かれています。
古代中国ではすでに戦国時代に人体解剖が行われていた可能性があります。
なぜなら、そのことをうかがわせる記述が黄帝内経には見られるからです。
しかし、厳密に言えば東洋医学の五臓は、現在の西洋医学による内臓とは別物です。
では、東洋医学の五臓六腑について少しだけ簡単に説明していきたいと思います。
五臓について。
・肝:血を蔵し、筋の運動を支配し、爪を養う。精神活動を支配する。
・心:血を全身にくまなく運行させ、生命活動にとって最も重要な役割を果たす。
一国の君主のような存在。
・脾:胃と一体となって働き、飲食物の消化・吸収をつかさどる。
・肺:気をつかさどり、全身に肺気をめぐらせ、呼吸や発声を行う。
皮膚を養い、鼻との関係も深い。
・腎:骨を栄養し、全身の水分代謝を行う。両親から受け継いだエネルギーを蓄える。
生命力の根源である元気をもたらす。耳との関係も深い。
六腑について。
・胆:胆汁を貯蔵し、決断を下したり、勇気を出す精神的な役割がある。
・小腸:胃から送られた飲食物のかすを水分と固形物に分ける。
・胃:飲食物が入る丸い袋状の器官。脾と共に消化吸収を行う。
・大腸:小腸から送られてきた飲食物のかすを転送しながら変化させ糞便として肛門から排泄する役割を行う。
・膀胱:尿を溜め、排尿する。
・三焦:特定の器官ではないが、水分代謝や、気や血、水分の調節をする役割がある。
西洋医学とは違う捉え方。
この様に、五臓の機能についての東洋医学の考え方は西洋医学のそれとは異なっている所があります。
西洋医学では内臓は脳などの中枢神経の命令で働くと考えています。
それに対して東洋医学の五臓は、精神活動や関係の深い体の構成部分に対して中枢的な役割を果たしていると考えます。
陰陽と五臓六腑。
東洋医学では「陰陽」と「五臓六腑」両方がとても重要な考え方の基本です。
従って、私たち鍼灸師は皆様のお身体の陰陽・五臓六腑の状態をさまざま角度から把握するひつようがあります。
そして鍼や灸を用いてバランスを調節していくのです。
東洋医学にご興味が湧いてきたという方。
体内のバランスを見て欲しいという方。
病院に行く程でも無いがお身体の不調に悩んでいるという方は是非お待ちしております。