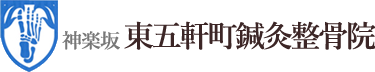人はなぜ噛みしめてしまうのでしょうか?
噛みしめ癖が取れずマウスピースを装着している方、奥歯がすり減っている方、寝てるまに奥歯を破壊してしまった方など様々です。
今は克服しましたが僕も以前は、ピアノで難しい曲の神経質なフレーズを弾く際にいつも喰いしばっていました。
なぜ喰いしばるのか?僕自身の噛みしめ行為の答えは「失敗したくない」と思うからです。そしてもう一つ、喰いしばると「今自分は頑張っている」と思えたからです。
力みと脱力。
脳にはミラーニューロンなる神経の働きがあります。これは、目の前の人や、興味がある人のしぐさや表情を無意識のうちに真似てしまうというものです。
もしかしたら噛みしめ癖のある人は身近に、噛みしめや常に力が入っている人がいて、無意識のうちにそれを脳がトレースしているのかもしれません。
例えばピアノ演奏の場などで言うと、演奏者が力むとそれを見ている人も自然と力が入ります。
人は喰いしばったり、力が入ると前かがみになります。「前かがみになる」とは一般的に「防御の姿勢」です。防御の姿勢は緊急時にとるものであり、緊急時は「力が入り硬く」なります。なぜ力が入って硬くなるかというと極論、血の巡りを悪くして戦いの際の出血を減らすためです。
いうなれば「力み」は命を守るための手段であり、一般的な芸術を行うには邪魔になる事が往々にしてあると僕は思います。なぜなら力むことで動きが悪くなるからです。
脳で感じたあらゆる感情や事象を自由に表現するには、柔らかくてしなやかでよく使い込まれた身体が必要です。それには基本的に脱力がなされていないと柔軟性は生まれません。
なぜ今、力む必要があると判断したのか?
冒頭で述べたように、僕が演奏中に噛みしめる理由は「失敗したくないから」と「頑張っている感じがするから」というものです。
そして、前述のように「力み」を紐解いていくと最終的には出血を抑制して命を守るためだと書きました。
…ならばなぜ、噛みしめる癖がある人や、脱力が上手く出来ない人は日頃から「命の危険」を意識しているのか?あるいは無意識のうちに危機を感じて「力み」がデフォルトになってしまっているのでしょうか?今、その人が置かれている状況は「失敗できない緊急時」なのでしょうか?
危機を感じる程のストレス。
噛みしめに関してはストレスが大きく関係しているといえます。
職場や家庭、学校など、一日の内で多くの時間を過ごす生活の主体となる場に敵がいたり、心身共に疲弊するミッションを請け負っていたりというのは多大なストレスです。さらに、逃げも隠れも出来なく、いつ終わりがくるのか先が見えない状態である事も常時臨戦態勢になりやすいでしょう。
睡眠中の無意識下の噛みしめと微小覚醒。
常時臨戦態勢というのは、睡眠中も無意識の「噛みしめ」という行為に現れ、「警戒、緊張状態」をデフォルトにしておいた方が生存率が上がると潜在意識、本能が判断したという事なのかもしれません。
その証拠に、睡眠中に噛みしめ癖がある人は微小覚醒(マイクロアラウザル)が多いとされています。微小覚醒とは睡眠中に僅か数秒、脳が覚醒するというものです。それが断続的に繰り返されているといいます。
そして微小覚醒と噛みしめは、微小覚醒が先です。
微小覚醒が起きる原因は、日中のドーパミンなどの神経伝達物質の不具合により起きているのではないかと考えられています。
つまり、ストレスを中枢神経系が感知して働く事で睡眠中に微小覚醒が起きて、微小覚醒がトリガーとなって噛みしめが起きるという順番です。
いずれにしても、噛みしめ癖があり微小覚醒が頻発している方は必然的に眠りが浅くなり、疲労回復が十分になされていない可能性が高くなることは言うまでもありません。
良い噛みしめ。
本来、適度でリズミカルな噛みしめを行うと、その圧が歯の底にある歯根膜受容体に伝わって三叉神経を介して脳に入る事で副交感神経が優位になりやすく、ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンが分泌されます。これらは多少なりとも快楽に関わる脳内神経伝達物質です。
「適度でリズミカルな噛みしめ」とは、食事中の咀嚼です。
基本的に食事行為は、身の安全が確保された状態でなくては行えないためリラックスや快の感情とリンクしています。
ストレスによる噛みしめは強くて持続的な圧であり、これはよくありません。
なので、ストレスが多い人はガムを噛むのが良いとされています。噛みしめは噛みしめでも、食事やリラックスを想起させる、適度でリズミカルな噛みしめを日中に行うことで、「今の状態はストレスではない」という事を脳に上書き保存していくというのが大切です。
噛みしめても意味ない事を脳に教える。
冒頭で、僕は噛みしめ癖を克服したと書きました。
その方法は2つです。
一つは「噛みしめを辞める事で得したという経験を脳に学習させる」事です。
噛みしめてピアノを弾くと指の経絡や筋膜と連動して引っ張られて、指の動きが悪くなる事を後に知り、難しいフレーズを弾く時は意識的に口を開けて弾くようにしました。
すると、本当に滑らかに弾ける感じがしたのです。最初は「なんとなく」でしたが、何度も弾いているうちに確実に噛みしめない方が指が良く動く事を実感し、それを意識的に実践するようになりました。なぜならその方が得だからです。
二つめは逆に「噛みしめると痛い思いをする事を学習させる」事です。
これは単純に、舌を少しだけ出してそれを上の前歯と下の前歯で挟んでおくのです。この状態で、「好きなだけ噛みしめろ」「ほら、噛みしめたいだけ噛みしめろよ」と脳にアプローチするのです。すると、噛みしめません。というか噛みしめられません。なぜなら舌を噛んでしまって痛いからです(笑)
単純な話ですが脳は、とくに痛みや恐怖に直結する大脳辺縁系という本能を司る領域は単純であり、一説によると2~3歳程度のレベルで物事を快か不快かで判断するそうです。
なので噛みしめない事で実際に得したという経験をさせて、噛みしめると強制的に痛みを伴うからやめろと脅すのです。「噛みしめ行為は意味ないからやめよう」と本能に解らせ、理性脳を納得させるのです。
ストレス由来ならば、脅威の排除もしくは離脱を考える。
ストレス由来の噛みしめも同様に、「噛みしめは意味ない」と教え込む事が基本となりますがそれだけでは弱く、根本解決しない可能性が高いです。
敵がいる場合や、自身が属している何らかのコミュニティが害悪でありストレス、ひいては噛みしめの原因となっているならば、脅威となる存在の排除やそこから離れる事が根本解決になるかもしれません。
しかしこれは「言うは易く行うは難し」で、そう簡単にはいかない事は重々承知しています。であれば、少しの期間でいいからそこから3日とか1週間とか離れてみて、その時の顎の疲れ具合や噛みしめ具合はどうかをセルフモニタリングしてみる事をお勧めします。
「湯治で病が治った」の意味。
医師の永田勝太郎さんが著した「痛み治療の人間学」という本には、線維筋痛症など原因不明の疾患や症状の多くは、3カ月間の湯治をすることで治る事が多いと書かれています。
湯治とは、病を治すために田舎の温泉地帯のようなところの宿泊施設に数カ月滞在して、毎日温泉に入るというものです。これのポイントは、温泉ではなく「今置かれている環境からの逃避と変化」であるという事です。湯治中はなるべく誰とも連絡は取らないようにして、今までの日常から解き放たれなくてはなりません。
そうすることで何らかの難治性症状が治る、もしくは軽減する人が実に7割近くもいるそうです。
そうなると、そこで改善が見られた約7割の人達の病は「人間関係を含めた環境的ストレス」が原因だったと考える事ができます。
数日から数週間出来る事なら生活環境を変えて、今のコミュニティや使命から離れてみてもしも症状が軽減もしくは消失するようなら、本格的に離脱を検討すべきだと思います。
まとめ
良い噛みしめと悪い噛みしめがあります。良い噛みしめは、リズミカルで軽い圧が歯根膜受容体にかかるというもので、リラックスしている食事を想起させるものです。悪い噛みしめは、強く持続的な圧がかかる、戦いや命の危機を想起させるものです。前者は副交感神経優位のリラックスの状態に、後者は交感神経優位の緊張状態になります。
噛みしめの原因は変なクセや思考、日常生活におけるストレスなどがあります。ストレスが常にある場合は睡眠も浅くなりやすく、睡眠時の微小覚醒がトリガーとなって無意識のうちに噛みしめるのです。
これを改善するには、ストレスからの離脱、または噛みしめを辞める事で得をした経験と、噛みしめると痛い思いをするという事を脳に学習させることが有効である可能性が高いと思われます。
ピアノは芸術であり、頭の中の感性や情熱を手指にフィードバックするにはレスポンスのよい「身体」が必要です。「芸の術」を行うのに適した身体は硬くてはダメなのです。柔軟性を得るには「脱力」が肝となります。
もしも、ピアノ演奏でどうしても噛みしめてしまうという方は是非参考にしてみてください。