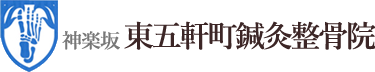認識を誤れば怪我をする。
○だと思い込んでいたら実際は△で怪我をする事はないだろうか?
なんで丸いはずなのに触ると痛いのか。
それはその物が△で先が尖っているから強く触れば必然的に怪我をする。
△なのに○の触り方をしていれば怪我をするのだ。
怪我をしたくなければ△なのだから△の触り方をしないといけない。
一体なんの話をしているのか読み手からしたら意味不明だろう。
しかし、人間関係含めあらゆるものにこの考えというか概念は当てはまると個人的には思う。
いわゆる「勘違い」「思い込み」にて失敗するという意味だ。
擬態。
例えば時代劇、ただのおじいちゃんだと思ってたら水戸の黄門様だった…。
推理ものなら、密室トリックかと思いきやアリバイトリックだった…。
学校で、「テスト勉強全くしてない」といいつつ裏で超勉強してる…。
自然界でも、
綺麗な花だと思ったら食虫植物だった…。
かわいい見た目をしていてとんでもない毒を持っていたり…など。
大抵の場合これらは「何らかの思惑」があってわざとそうしている。
なぜ擬態を使う?
仮に本人にはその意識がなかったとしても「目的達成」や「環境適応」あるいは「生き残るため」に「擬態」を使っているのだ。
相手の擬態に気づかなければこちらは対応を誤る。
対応を誤ると、必然的にこちらの予測とかけ離れた結果となる。
それだけならまだいい。
悪ければ不利益を得る。
そしてこれは何も人間関係や動植物だけではない。
例えば、お得に見せかけて利用者に契約を結ばせ、実際は長期で見ると全然お得ではないとか。
なんらかの制度やシステム、宣伝やキャンペーンなど、擬態は基本的に「利己のための悪知恵」だ。
擬態に惑わされなくば怪我はなし。
とすると、擬態に惑わされて怪我をするというのは結局、受け取る側の脳の問題なのだ。
勘違いや思い込みで脳にバイアスがかかっている状態。
「こうあるべき」「そのはずだ」という色眼鏡で見てしまって、勝手に解釈しているのだ。
なので、相手の立場になって考える事が大切だ。
相手の立場で、何の利があるのか様々な帰結を予測しながら、まっさらな目で物事の本質を見極める事が肝要となる。
そして、○なら○の、△なら△の、□なら□の形を正しく認識し、それに添った行動を、対応をしていれば決して怪我はしない。
当たり前のことだけど大切な事だ。